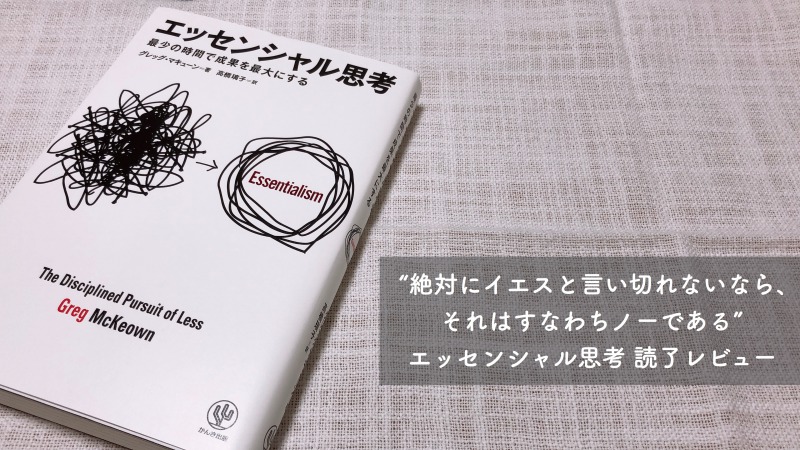「大人になったら、もう英雄はいらない」|池澤夏樹「ヤー・チャイカ」
少し前に「スティル・ライフ」の記事を書きました。
この本にに収録されているもう一つのお話、それが「ヤー・チャイカ」。
文彦と、彼がパーキングエリアで出会ったロシア人クーキンの会話を中心に展開されるお話。
物語は、ディプロドクスや文彦の娘:カンナの視点も交えながら進んでゆくのですが、今回はあえて深掘りはせず、さらりと魅力をお伝えできればと思います。
パーキングエリアでの出会い
物語は、文彦が一人娘のカンナを残して出張へゆくところから始まります。
出張中、仮眠を取るために入ったパーキングエリアで文彦は車が故障したというロシア人・クーキンと出会います。
二人はその後も少しずつ交流を重ね、たまにカンナを交えつつ友情を育んでいくのですが、このクーキンさん、とにかく話がうまい。
この話術が「この人、まさか……」という疑念の種にもなるのですが、こちらは盛大なネタバレになるのでそっとしておきましょう。
バイカル湖の霧
さて、クーキンが語るお話の中には、美しくも凛としたロシアの自然、その驚異が霧という形で登場します。
霧、というとあんまり危険な気がしないけれど、クーキンさんはその霧に一度命を持っていかれそうになっています。
戻りはじめて間もなく、わたしは凍った湖面の上に何か白いものが流れているのに気づきました。霧なのです。上を見ると空は青く晴れています。背筋がひやっとしました。町の中でも、霧はたちまち何も見えなくしてしまいます。
地上ではひとりの人間が生きるか死ぬかの瀬戸際に立たされているのに、いつもどおりの青く澄んだ空が見える。
自分は死ぬほど大変な思いをしてるのに、世界はまるで気にしてない。
世界の方は、あまりきみのことを考えていないかもしれない。
池澤夏樹「スティル・ライフ」
なんとなく、スティル・ライフの冒頭部分を彷彿とさせるシーンだなあ……なんて思うと同時に、クーキンに不思議な親近感を覚えてしまいました。
そういうときって、青空とかすごくきれいに見えますよね。その綺麗さが心に突き刺さる。いっそ、曇りや雨の日のほうが、心は楽かもしれない。
世界の方が気にしてなくても、こっちは気にしちゃうんだよね。
世界から見れば「取るに足らない悩み」だけど、自分にとっては「けっこう大きな悩み」。それが、誰かの悩みとの対比ではなくて、自然や宇宙といった「人間が暮らしている場所、空間」との対比で描かれるというところが素敵。
なぜなら、自然や宇宙の前では「いい人」を演じる必要も「頑張る」必要もないのだから。
大人になったら、もう英雄はいらない
世界初の女性宇宙飛行士であるテレシコワについて、文彦とクーキンが語る一幕にて、このセリフが登場します。
大人になったら、もう英雄はいらない。
大人になったら、もう英雄はいらない。
裏を返せば、子どもには英雄が必要ということ。
英雄を必要としている間は子どもである、ということ。
大人になったら目の前にある現実がすべてという世界で生きることが多くなります。
もしかしたら、自分が誰かの英雄になっていたり、夢を叶えていたりすることもあるかもしれません。あるいは、かつて夢見た人や、理想とした生き方に、どこか違和感を覚えるようになることだって、あるかもしれない。
それが前向きなことか、望まぬことかはわからないけれど、とにかく、『英雄』は必要なくなる。
英雄を必要としなくなった大人二人が語り合う場面に居合わせたのが、まさに英雄を必要としなくなりかけている文彦の娘・カンナだというのもまた、素敵。
霧に消えたディプロドクス
さて、カンナの視点になると物語は少しだけ分かりづらくなります。
少しの改行を挟んで、唐突に「わたし」目線で世界が語られるのですが、突然「恐龍」の「ディプロドクス=ディッピー」が登場したり、「わたし」はディッピーをマンションで飼っていたり。
最初、カンナはこう話すのです。
わたしは老婆になってもまだディッピーにこの乾草をやっているでしょう。その時になって、もしも乾草を買うお金がなかったら、わたしは悪いことをするかもしれません。
ここからはわたしの勝手な推測ですが、『ディプロドクス=英雄≒夢』と捉えた場合、このときのカンナは『夢のためなら何でもする』『夢のためならなんだってできる』と思っている純粋な子どもの性格が強いように思います。
一方、少しお話が進むと、カンナの心境にも変化が生まれ始めます。
前にわたしは、自分はおばあさんになってもディプロドクスに餌をやっているだろうと書きました。そのためのお金がなかったら悪いことでもすると言いました。
でも、本当の話、わたしはそんなに長い間ディッピーを飼ってはいられないだろうと思います。わたし自身にその資格がなくなる日がいずれ来るような気がするのです。
この、「わたし自身にその資格がなくなる日」が来るかもしれない、という感覚、誰しもが体験したことがあるんじゃないかなと思うのです。
体操をしているカンナの場合は、「もうこれ以上やっても伸びないと思う」という形で限界を感じたようですが、怪我だったり、センスの限界だったり、「夢と別れを告げなければいけないのかもしれない」と思う理由は人それぞれ。
そして(という三文字では語り尽くせないほどの出来事を経て)「ヤー・チャイカ」は終わりを迎えるのですが、このシーンがとても美しい。
ふたりのわたしと遅効性の解答
ふたりの「わたし」とディプロドクスによって、静かに幕が降ろされるのです。
ひとりめの「わたし」は、ディプロドクスの頭に乗って揺られています。大好物の葉っぱのある方角とは「逆向き」に進み、シダのような「奇妙な葉っぱ」を食べるようになったディッピーと共に、深くなりゆく霧をながめているのです。
もうひとりの「わたし」は、上で記した「わたし」を遠くから眺めています。
はっきりと違う道を歩み始めたふたりの「わたし」は、静かにゆるやかに、それぞれの人生を歩み始めます。
ディプロドクスの頭に乗ったわたしも、だんだんに見えなくなります。そういう風にしてわたしは自分と別れを告げ、そうしてわたしは新しい自分になるのだと、見ているわたしにはわかりました。
もうひとりの「わたし」がどうなったかについては、作中で文彦がちゃんと答えを示してくれています。
分かれ道で一方を選んだら、もう一つがどういう道だったのか、推定するほかない。(中略)今となってはわからない。
はっきりと、読者が抱いていた疑問に寄り添ってくれているような気がします。
どっちを選ぶのが正解だったのかということではなくて、分からないという感覚は間違っていないんだよ、と優しく語りかけてくれているみたい。
……ここまであまり触れてこなかったですが、ずっと思っていたことがひとつ。
上で示した「別の道を進んでたらどうなったんだろう?」という読者の問いに、文彦が答えているのは(本人にその気があったかどうかは別として)およそ50ページほど前。
最後、ディプロドクスとわたしを見送った「現実を生きるわたし」は霧の中に立っているので、クーキンさんの体験を考えるなら右も左も分からない真っ白な世界にいるわけですが、ここが真っ暗闇じゃないのも、そして空を見上げれば(たぶん)青空が見えているだろうというところも、わたしの心に刺さったポイントです。
なにをするために、どこに行けばいいか分からない。
これに対しても、文彦は確かな答え――というよりも、支えを残してくれています。
本当にしたい仕事をみつける暇はまだたくさんある。
まとめ
この小説は、読むというよりも感じると言った表現がしっくりくる作品。
心に残ったシーンを断片的につないで、わたしなりの解釈を交えてのご紹介でしたが、少しでも心に触れるものがあったのなら、ぜひ手にとって読んでみてください。
夢を諦めないで叶えました! という小説が多い中、本作は「夢を諦めたのは、新たな自分への第一歩」として前向きにとらえているところがとても好きです。
戸惑いそのものを受け入れてくれるような柔らかな世界観の「ヤー・チャイカ」。
人生の岐路に立っているすべての人におすすめしたい一冊でした*
それでは*
こんな人におすすめ
- 人生の岐路に立っている
- やりたいことが見つからない
- あのとき選んだ道が正しかったかどうか、考えることがある
- 北の国、雪国が好き